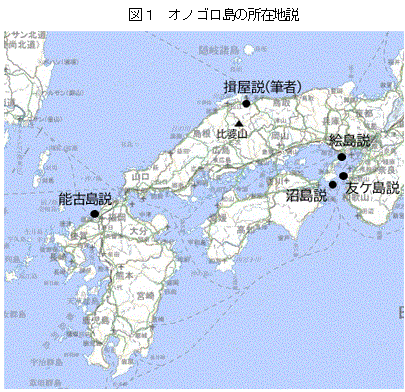gooブログ「ヒナフキンのスサノオ・大国主ノート」に「スサノオ・大国主建国論6 壱岐・対馬の海人族の国生み神話」をアップしました。https://blog.goo.ne.jp/konanhina
古事記は「高天原(たかまがはら)」での「別天神(ことあまつかみ)五柱」「神世七代」から始まっていますが、前回の「別天神(ことあまつかみ)五柱」「神世七代」に続き、その最後の伊邪那岐(いやなぎ)・伊邪那美(いやなみ)(以下、イヤナギ・イヤナミと表記)のオノゴロ島への「天降り」、「14の島生み」について分析しました。
この「オノゴロ島」については、淡路島北岸の淡路市「絵島説」(本居宣長)、淡路島南の南あわじ市「沼島説」、淡路島東の和歌山市「友ケ島(沖ノ島)説」、福岡市の「能古島説」(古田武彦)などがみられますがが、私は「オノゴロ」という島名の由来、イヤナミの名前と墓所、イヤナミを祀る揖屋神社からみて、出雲の意宇川河口の東出雲町の「揖屋説」を提案してきています。
「14の島生み」は淡路島を起点として「行きは西行、還りは東行」の順の島生みなら問題ないのですが、太安万侶は「行きは西行、還りも西行」で書き、彼一流の「天皇家を中心とした歴史を書きながら、スサノオ・大国主一族の真実の歴史を秘かに書き残す」という表裏表現、真偽表現をここでも行っており、壱岐・対馬の海人族のイヤナギは「行きは東行、還りは西行」で米鉄交易圏を広げていった歴史をちゃんと示しています。
また、イヤナギが降り立ったオノゴロ島には「八尋殿」があったというのであり、「八尋」は両手を広げた長さの「尋」(1.8m)の8倍で14.4mになり、青森市の三内丸山遺跡の大型建物の長さが15m、出雲大社の正面幅13.4mとほぼ合致していることからみても、縄文時代からイヤナミ、大国主の時まで同一スケールの建築技術が続いていたことを示しているのです。
私は太安万侶は中国の司馬遷に匹敵する「史聖・太安万侶」と考えています。司馬遷は直球ですが、太安万侶は変化球であり、推理力を働かせ、複眼的に読まないと真実の歴史は見えてこないのですが、見事に紀元前1世紀~紀元4世紀のスサノオ・大国主建国の真実の歴史を伝えているのです。太安万侶の暗号、みなさんも読み解いてみたいと思いませんか?―拙著『邪馬台国探偵団~卑弥呼の墓を掘ろう~』参照
本ブログのテーマの「縄文社会論」としても、縄文文化・文明とイヤナギ・スサノオ・大国主建国が連続しているということを、「ポスト縄文社会論」として参考にしていただければ幸いです。陳寿や太安万侶を馬鹿にすることなく、読んでみていただきたいものです。雛元昌弘
□参考□
<本>
・『スサノオ・大国主の日国(ひなのくに)―霊(ひ)の国の古代史―』(日向勤ペンネーム)
・『邪馬台国探偵団~卑弥呼の墓を掘ろう~』(アマゾンキンドル本)
<雑誌掲載文>
2012夏「古事記」が指し示すスサノオ・大国主建国王朝(『季刊 日本主義』18号)
2014夏「古事記・播磨国風土記が明かす『弥生史観』の虚構」(前同26号)
2015秋「北東北縄文遺跡群にみる地母神信仰と霊信仰」(前同31号)
2017冬「ヒョウタンが教える古代アジア”海洋民族像”」(前同40号)
2017冬「スサノオ・大国主建国論1 記紀に書かれた建国者」(『季刊山陰』38号)
2018夏「スサノオ・大国主建国論2 「八百万の神々」の時代」(『季刊山陰』39号)
2018夏「言語構造から見た日本民族の起源」(『季刊 日本主義』42号)
2018夏「スサノオ・大国主建国論3 航海王・スサノオ」(『季刊山陰』40号)
2018秋「『龍宮』神話が示す大和政権のルーツ」(『季刊 日本主義』43号)
2018冬「海洋交易の民として東アジアに向き合う」(前同44号)
2019春「漂流日本」から「汎日本主義」へ(前同45号)
<ブログ>
ヒナフキンのスサノオ・大国主ノート https://blog.goo.ne.jp/konanhina
ヒナフキンの縄文ノート https://hinafkin.hatenablog.com/
帆人の古代史メモ http://blog.livedoor.jp/hohito/